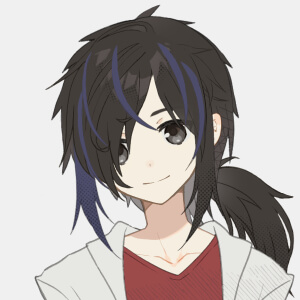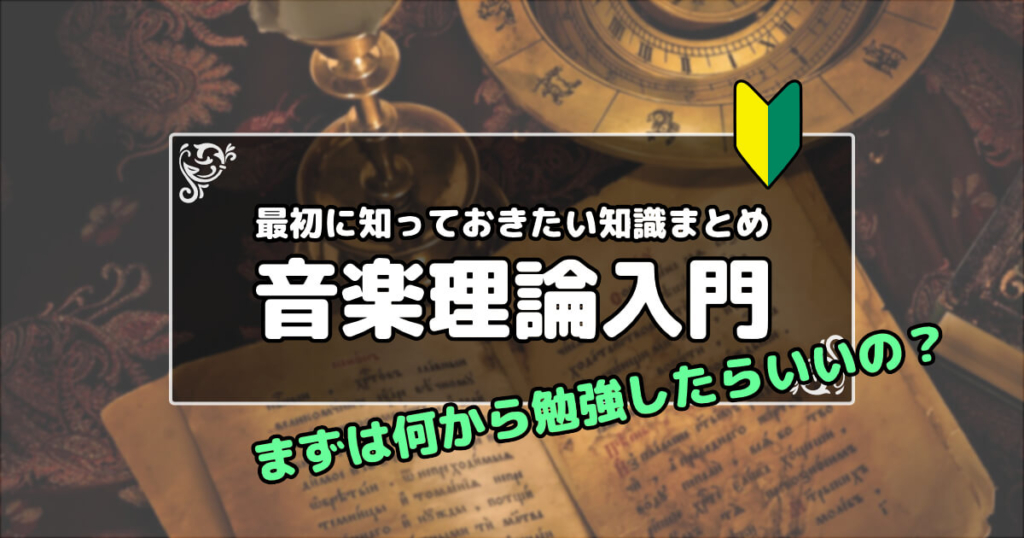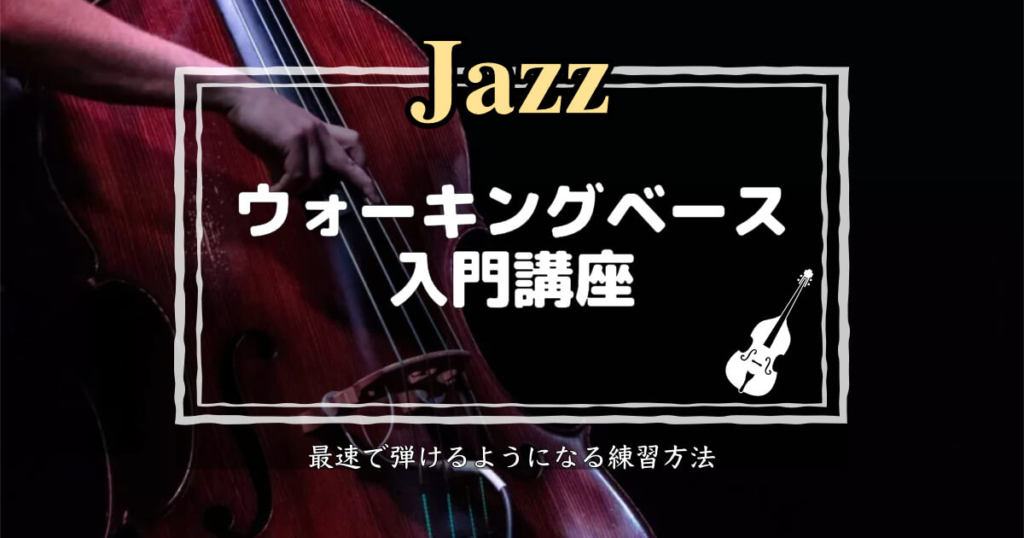
ウォーキングベースの基本について
ウォーキングベースとは
厳密に「これがウォーキングベース!」という定義やルールが定まっているわけではありません。
――が。
一般的には、Jazzのベースラインと聴くと誰もが思い浮かべる「4ビートで音を歩くように繋げていくベースライン」のことをウォーキングベースと呼びます。

これです!
4分音符で音を繋げていくベースライン、これがウォーキングベースの雰囲気です!
ロックで一般的に使われる「ルート弾き」のベースラインとは全然違う雰囲気がありますね!
4ビートとは
4分の4拍子で、4分音符を基本単位としたビートのことを4ビートと呼びます。
ざっくりと「4分音符をメインに演奏する音楽」と覚えておきましょう!
ウォーキングベースってどうやって弾くの?
難しそうなイメージを持たれがちなウォーキングベースですが、ベースラインを構築する基本ルールは至ってシンプルなんです。
- コードトーンを踏みながら指板上を4ビートで歩く[重要度★★★★★]
- 経過音を使って滑らかに音をつないでいく[重要度★★★★]
- 1拍目はルートを弾いてあげると親切[重要度★★]
いずれも100%守らなくてはいけないというものではありませんが、最低限この3点を頭に入れておけばウォーキングベースの基本は完璧です!
基本をおさえてあげれば、誰でもかんたんに弾けるようになります!
かんたんに弾けるからこそ、Jazzという一期一会で演奏するような世界で普及したのです!
ウォーキングベースの弾き方
1. コード進行を確認する
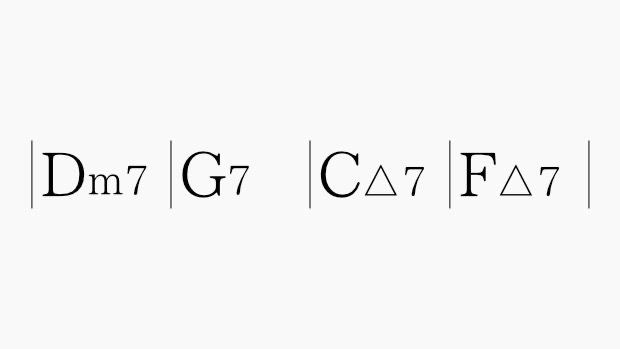
ウォーキングベースを演奏するときには、最初にコード進行をしっかり確認しましょう!
2.指板上でルートの位置を確認する
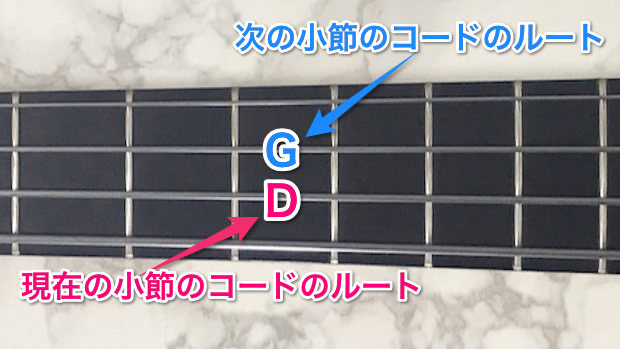
指板上のスタートの位置と、次に着地するルートの位置を把握します。
1小節目を演奏している段階で、頭のなかでは2〜3小節先のルートが見えている状態が理想です!
3.コードトーンを経由しながら次のコードのルートを目指す
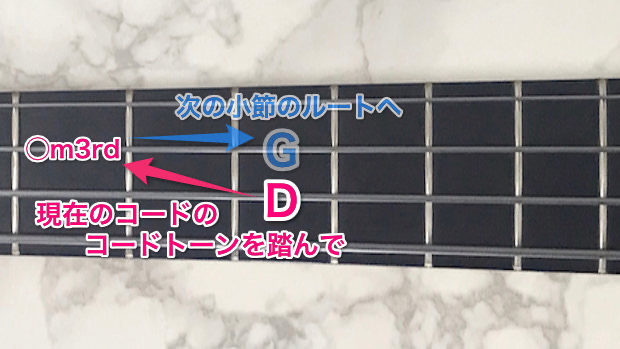
コードの構成音を踏みながら、次の小節のルート音を目指します。
これがウォーキングベースの基本構造です。

ウォーキングベースの練習方法
僕が生徒さんにオススメしているウォーキングベースを最短で習得する方法は
「同じ曲のベースラインを3パターンぶんコピーする」
という練習方法です。
本当に即効性があるのでオススメです!
これで弾けるようにならないなら「自分はジャズ向いてないから一回レッスン受けよう…」と思ってください。
そのくらい簡単に誰でも弾けるようになります!
例えば、Joseph Kosma氏のAutumn Leaves(枯葉)。
ジャズを勉強する人なら絶対に避けては通れない、超定番のスタンダード曲です。
- Al Cohn & Z oot Sims版: Either Way
(Ba: Bill Crow) - Cannonball Addeley版: SOMTHIN’ ELSE
(Ba: Sam Jones) - Chet Baker版: She Was Too Good to Me
(Ba: Ron Carter)
などなど、名だたるミュージシャンたちがこの楽曲を演奏しています。
このAutumn Leavesのベースラインを、まずは数パターンコピーしてみましょう!
Jazzは先人の演奏を聴けば聴くほど上手くなるジャンルです。
ベースの巨匠たちが奏でるベースラインをたくさんコピーしてみましょう!
ジャズ・スタンダードの楽曲から練習し始めるのがオススメです!
最速でウォーキングベースが弾けるようになる方法
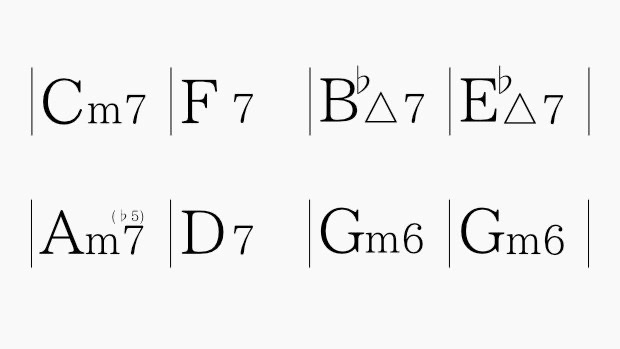
題材として、Autumn Leavesの冒頭8小節のコード進行を取り上げてみます。

例えば、こちらはパターンAのウォーキングベースライン。

そして、こちらがパターンBのベースラインです。
この2パターンのベースラインをですね。
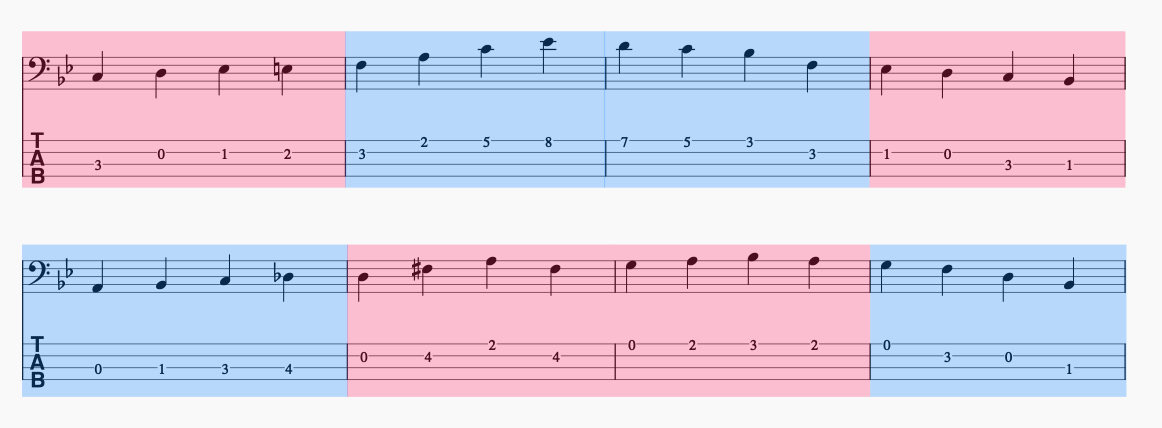
ばばばばん!
テキトーに融合させます。
どうですか!
これだけで自分だけのウォーキングベースができちゃいました!
小節ごとにフレーズを覚えていこう
「同じ曲のベースラインを3パターンぶんコピーする」
これを何曲もやっているうちに、
- 4度上に向かう小節のベースライン
- 4度下に向かう小節のベースライン
- II-V-Iの進行に対応したベースライン
というように1小節単位で自分のなかにウォーキングベースの引き出しが蓄積されていきます。
お決まりの手グセのような感覚で、指が覚えてくれます。
あとはコード進行に合わせて、自分のなかに蓄えられたフレーズの引き出しを並べていくだけ。
ね、簡単でしょ?
まずは難しく考えずに、ウォーキングベースの雰囲気を楽しむところから始めてみましょう!

演奏中には、常に頭のなかで「理論的なコード進行の分析」と「分析したコード進行に対応するウォーキングベースの手札」が展開され続けています!
本質的なウォーキングベースラインの練習講座
本来ならウォーキングベースは、音楽理論を駆使しながら「より滑らかに」「より美しく」「そして自分らしく」を追求しながら演奏するのが醍醐味なんですけども。
音楽理論なんて難しすぎてよく分かんないです!
耳コピは苦手で面倒くさいです!
なんか手っ取り早く弾ける方法ないですか?
という方のために、即席でなんちゃってベースラインが弾けるようになる練習方法を解説します!
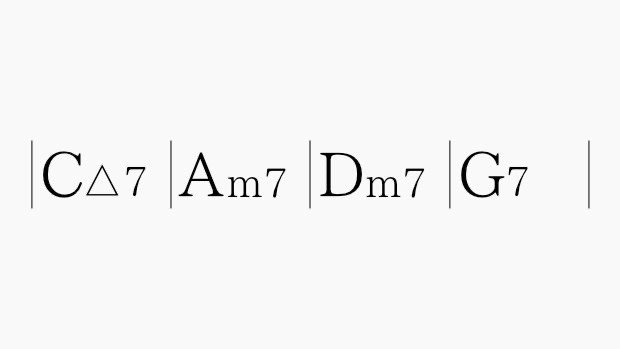
Key=CのII-VI-II-Vの進行で解説します。
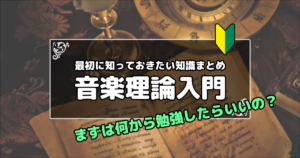
1.ルート
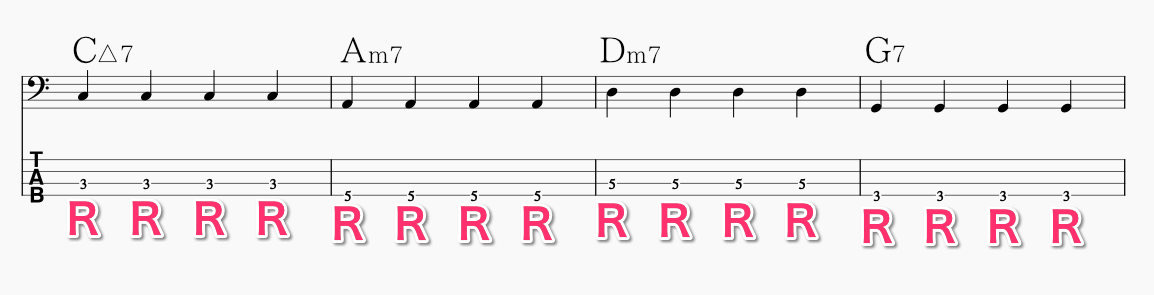
【第1の要素】
まずは4ビートのルート弾きでウォーミングアップです。
4ビートのベースラインはリズムの誤魔化しが利きません!
コードの変わり目でリズムがヨレないように気をつけましょう!
2.ルート+5度
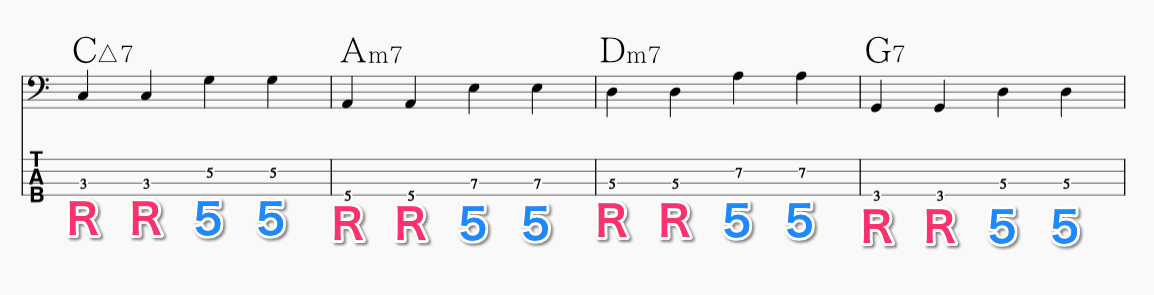
【第2の要素】
ルート弾きが安定してきたら、3拍目と4拍目を5度の音に変えて演奏してみましょう。
オクターブの上下はどちらを使用してもOKです!
3.ルート+3度+5度
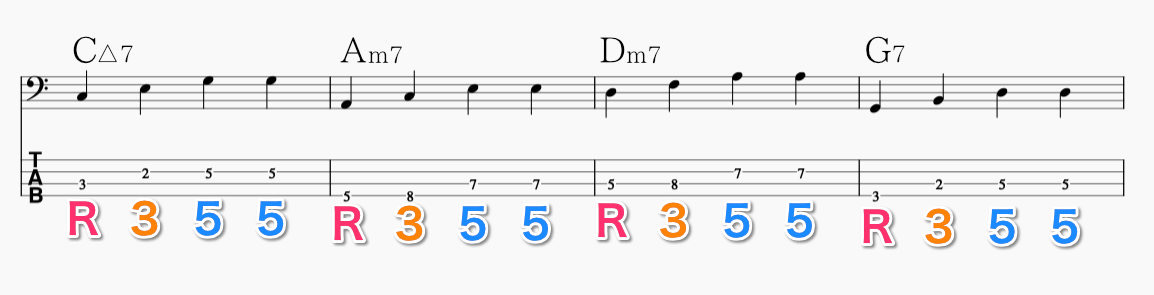
【第3の要素】
ルートと5度で演奏できるようになったら、 次は3度の音を追加してみましょう。
2拍目を3度に変えて、トライアドのコードトーンを順番に演奏します。
メジャー系のコードではM3rdを、マイナー系のコードではm3rdを弾きましょう!
4.ルート+3度+5度+アプローチノート
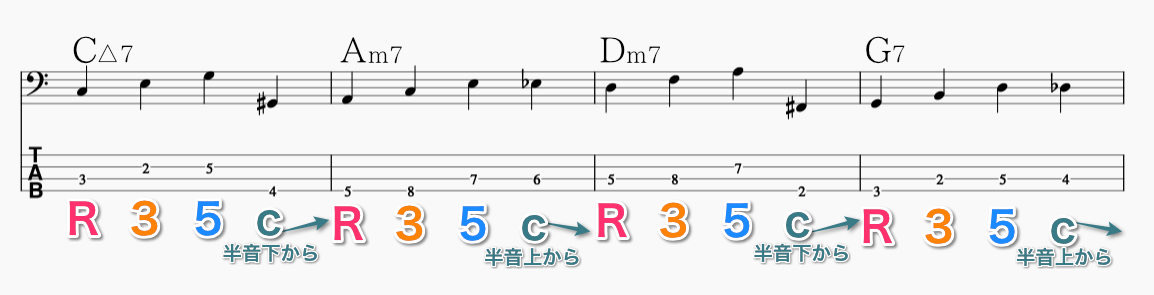
【第4の要素】
4拍目の音を、次のコードのルートから見て半音上または半音下の音を追加してみましょう。
この例の場合だと2小節目のルートがAなので、その半音下のG#もしくは半音上のA#を踏んでからAに向かうことになります。
この一手でいっきにウォーキングベース感が付加されます!
半音階のことをクロマチック(chromatic)と言います!

5.他のコードトーンにもクロマチックアプローチ
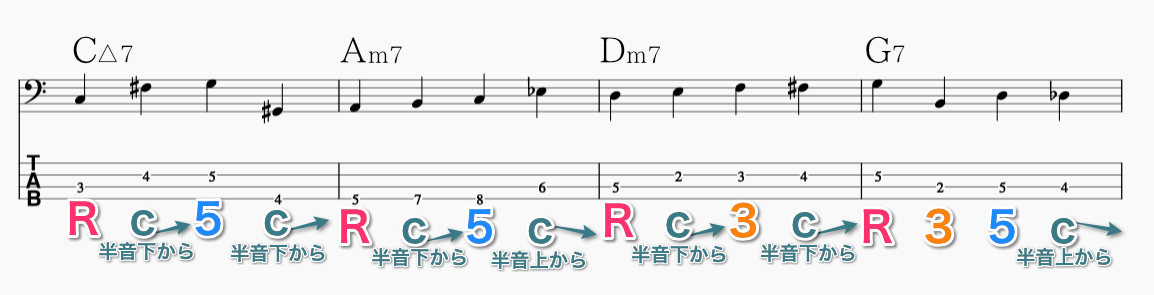
【第5の要素】
慣れてきたら、各コードトーンに向かって自由に半音階でアプローチしてみましょう。
- 3度に向かう半音
- 5度に向かう半音
- 7度に向かう半音
- 次の小節の3rd, 5th, 7thに向かう半音(応用)
などなど。
クロマチックアプローチでコードの構成音を広いながらウォーキングベースのラインを組み立てていきましょう!
奇数拍(1・3拍目)ではコードトーンを、偶数拍(2・4拍目)ではアプローチノートを弾くように意識するとウォーキングベースらしいベースラインが作りやすいと思います!
美しいウォーキングベースを演奏するコツ
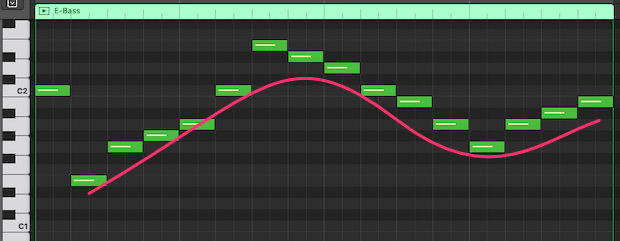
五線譜やピアノロールで見たときに、綺麗な階段状になるようなベースラインが理想的です。
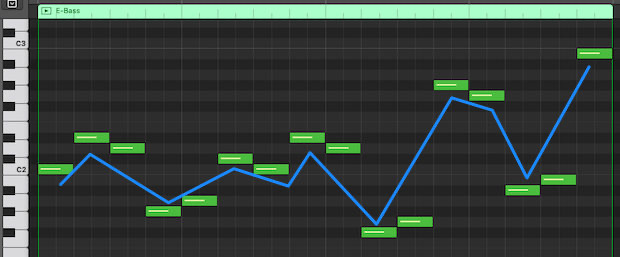
こちらは悪い例。
「コードトーンに対してクロマチックアプローチ」というルールはそのままですが、このようなアレンジだとピアノロールで見るとガタガタです。
必ずしも間違いというわけではありませんが、これではウォーキングベースらしい響きとは言えないと思います。
音がなめらかに繋がるように経過音を混ぜてあげるのがウォーキングベースらしく聴かせるコツです!
たくさんウォーキングベースのフレーズをコピーしていくと、なめらかに音をつなげるアレンジ方法が感覚的に分かってきます!