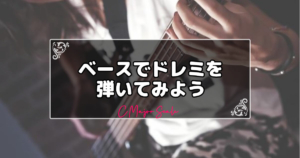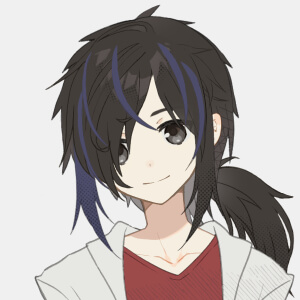初めて楽器の世界に足を踏み入れた人には、なかなか馴染みのない「CDEFGABC」というアルファベットの音名。
これは、ドレミファソラシドを言い換えた言葉になります。
意味は同じです。
『Aマイナー』とか『Fコード』という呼び方を、一度は聞いたことがあると思います!
音楽の世界――、とくに楽器の界隈では「ドレミファソラシド」という呼び方は滅多に使いません。
音名を指すときは「CDEFGABC」というアルファベットを使って会話をします。
音名をアルファベットで分かるようになれば
世界中のミュージシャンと共通言語で会話が出来るようになります。
楽譜が見つからない曲も自由に演奏できるようになります。
一生使い続ける知識なので、ちょっとだけ頑張って覚えてみましょう!
ドレミファソラシドをアルファベットで覚えよう
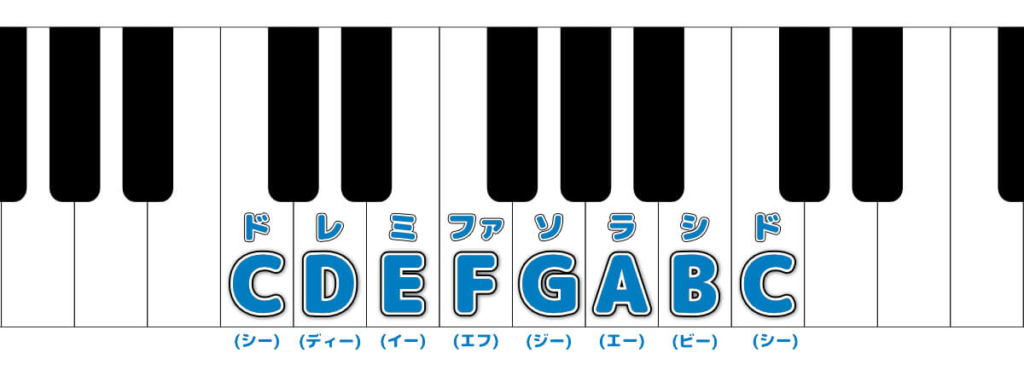
まずは黙って丸暗記だッ!!!
……え、あの、説明とかないんですか?
まずは何も考えずに覚えてください!
これがすべてです!
脳筋!ふぁいっ!
冗談抜きに、音名に関しては「こういうものだ」と思って丸暗記する以外にありません。
これとまったく同じ感覚で「ドはC」「レはD」と決まっているので大人しく従って覚えるしかありません。
読み方は普通のアルファベットの読みで「シー,ディー,イー,エフ,ジー,エー,ビー」です。
- 使うアフファベットはA〜Gの7つ
(ドレミファソラシの7音ぶん) - ドがC
- Aはラ
この3点だけしっかり覚えておけば、あとは使っているうちに自然に頭に入ってくると思います。
「ドレミファソラシド〜♪」の音程で「CDEFGABC〜♪」と歌って覚えちゃいましょう!
指板で覚えるドレミとCDE
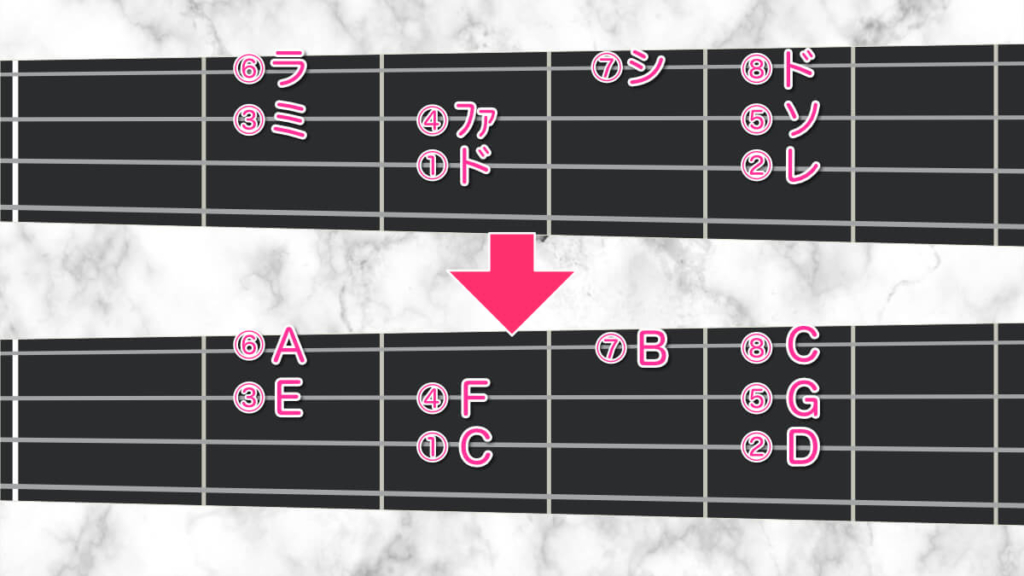
指板で見るとこんな感じ。
実際に楽器でメジャースケールを弾きながら「CDEFGAB」の音とその位置を確認してみてください!
音名に関する雑学
ドレミファソラシドはイタリア語
Do Re Mi Fa Sol La Si
僕たちが子供の頃から使ってきた「ドレミファソラシド」は、イタリア語の音名なんです。

日本語では「ハニホヘトイロハ」になります。
小学校の頃の音楽の時間に、「ト短調」とか「ハ長調」とか聞いたことがあると思います!
あれです!
CDEFGAH
ドイツ語では「ツェー, デー, エー, エフ, ゲー, アー, ハー」ですね。
クラシック畑の方や吹奏楽経験者の方には、馴染みのある音名だと思います。
CDEFGAB
音楽の世界で標準で使われている「CDEFGAB」はアメリカ・イギリス式。
ちなみに、アメリカ本国でも普通の人は我々と同じように「ドレミファソラシド」を使って会話しているそうです!
どうしてド=Cなの?
なんでCから始まるんですか?
一言でまとめると「本来の音楽の基準はA(ラ)だったけど、時代の流れのなかで軌道修正されたから」です。
その大元の起源を辿ってみると
- 「赤ちゃんの産声の高さがAだから」説
- 「古代ギリシャの旋律の基準がAだったから」説
- 「男性の発声できる最低音がγ(ガンマ=G)で、その1音上のAを基準にしたから」説
などなど、諸説ありなんですけども。
世界の世界でA(440Hz)が重要な音であることは間違いありません。
分かりやすいところだと、オーケストラのチューニングは440Hzを基準に合わせます。
「ピ・ピ・ピ・ピーン♪」でおなじみの時報の音も440Hzです。
ギターやベースのチューナーも、デフォルトでは440Hzが基準に設定されています。
それから長い時間を経て、17世紀以降には
「やっぱりC(ド)をスタートにしたほうが明るい響きで使いやすいんじゃね?」
ということでCから始まる音階が標準になっていきました。
現代の五線譜でも、中心の音はCになっています。
音楽史は”諸説あり”だらけの世界なので「ふ〜ん、そうなんだ」くらいに思っておいてください。