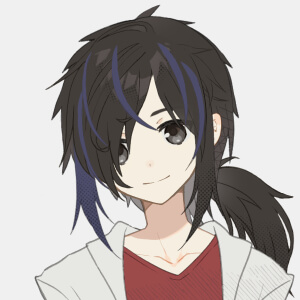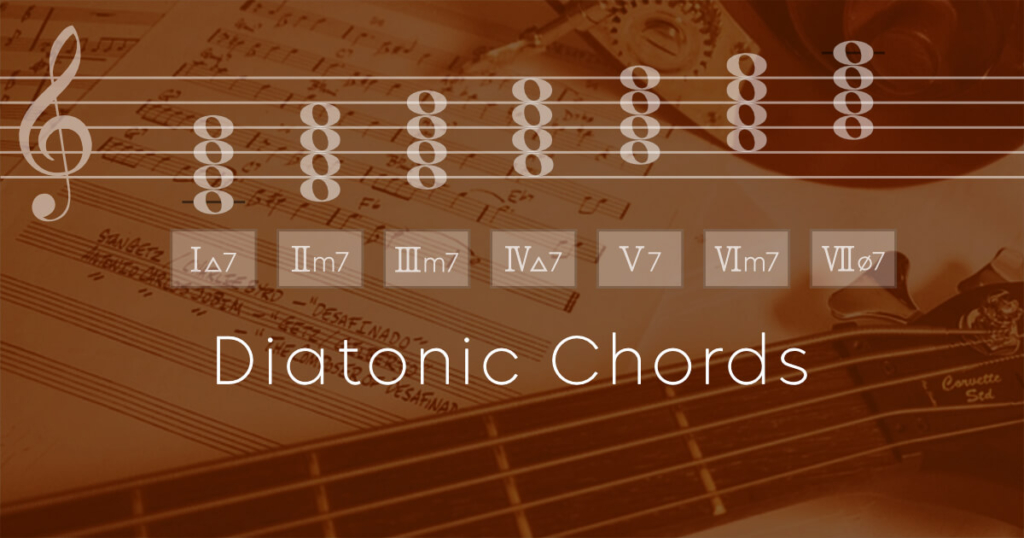
ダイアトニックコード。
音楽理論の理論書を購入すると、だいたい本編の最初の1ページ目で紹介されている内容です。
算数で例えるなら「足し算のやり方を勉強しよう!」みたいな部分です。
ダイアトニックコードとは、スケール上に成り立つコードのことです。
なんて?
大丈夫です!
しっかり分かりやすく解説します!
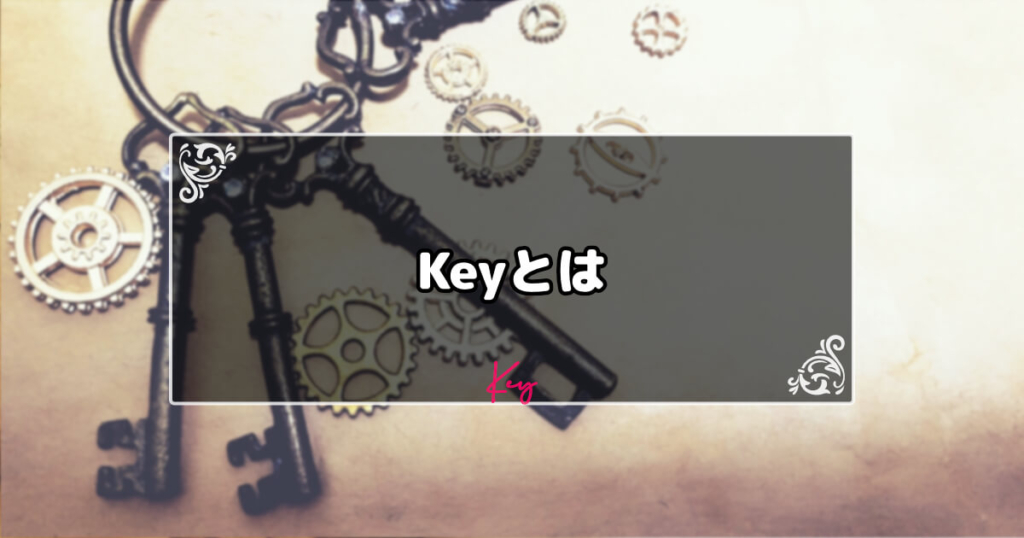
「曲のキーって何?」の記事で事前に勉強しておくと、分かりやすいと思います!
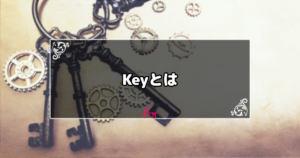
ダイアトニックコードとは
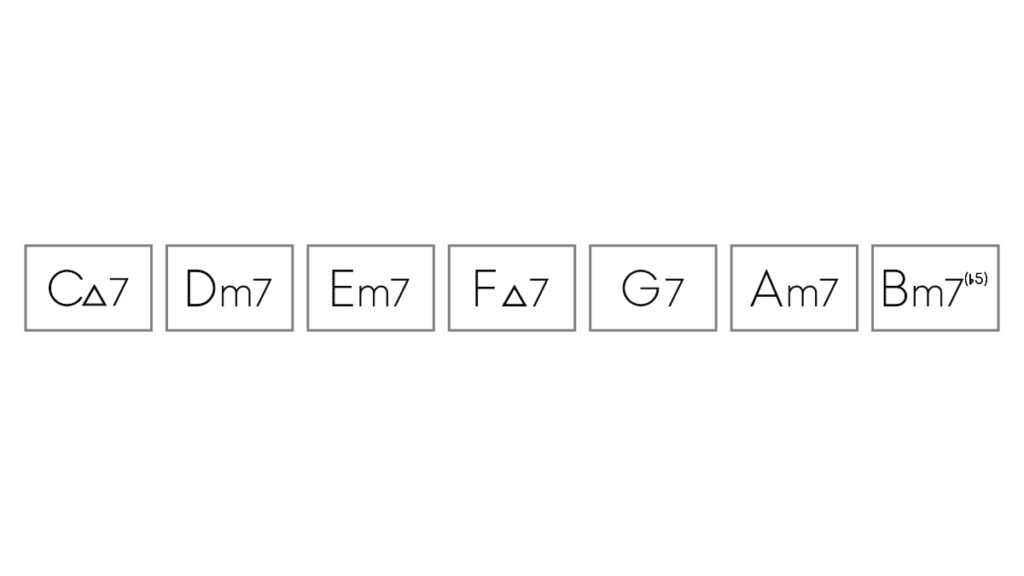
ある特定の条件によって構成された7つのコードの集まりのことを「ダイアトニックコード(Diatonic Chords)」と呼びます。

7つのコードには、それぞれ「機能(Function)」が備わっています。
コードの響きの特性のようなものですね。
我々ジャズミュージシャンは常に頭の中でダイアトニックコードとその機能が思い浮かんでいて、それを演奏に活用しています!

ダイアトニックコードの成り立ち
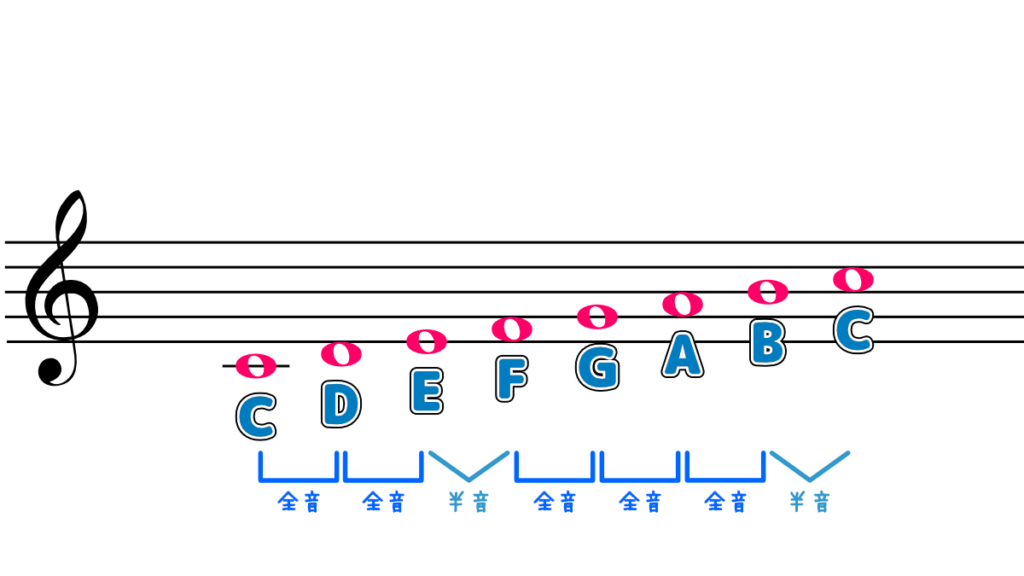
まず例としてCメジャースケールを用意してみました。
Key=Cの楽曲を構成する7音を並べたスケールです。
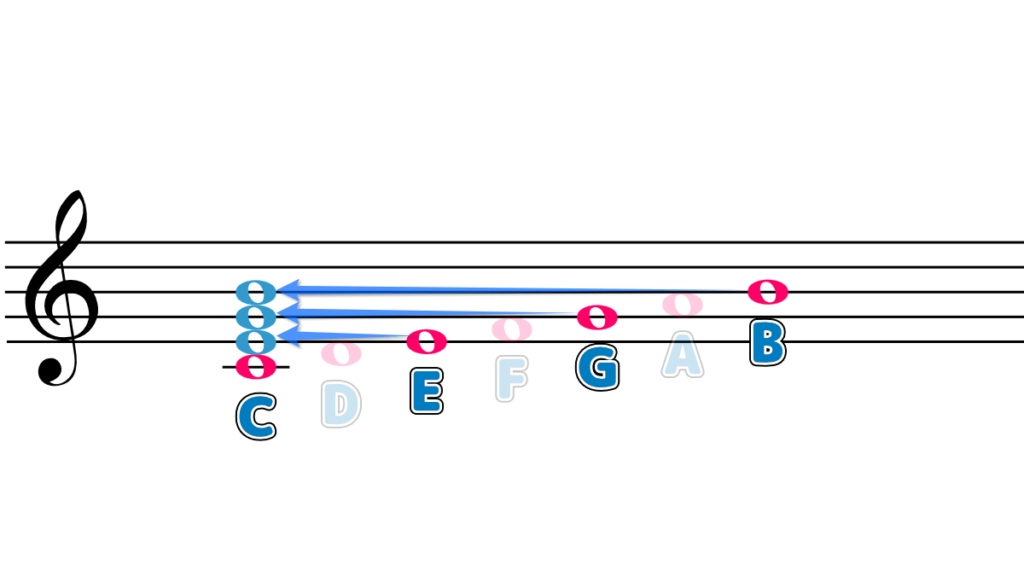
スケールの音をひとつ飛ばしで重ねていくことで、和音(コード)が完成します。
一番低い根音(ルート)を1度として、3度・5度・7度の音を重ねます。
これが「コード」を構成する基本的な考え方です!
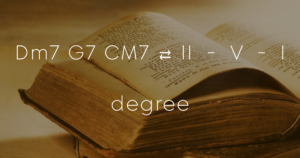
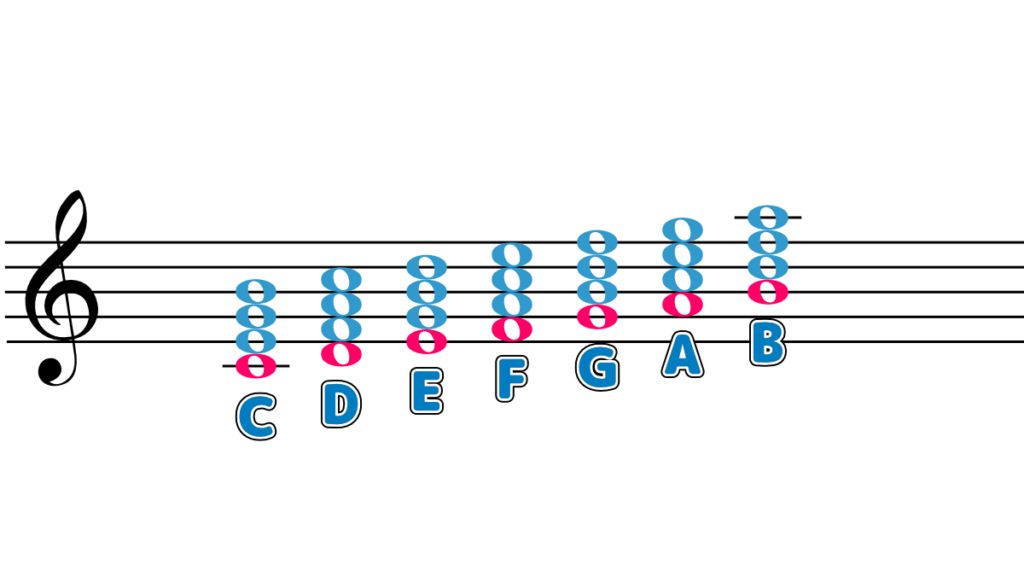
- Cの上にはE,G,B
- Dの上にはF,A,C
- Eの上にはG,B,D
…というように、スケールの各音の上に1音飛ばしで3つずつ音符を重ねてみました。
ここで完成するのがKey=Cの曲の中で使える7つのコード、すなわち「ダイアトニックコード」になります。
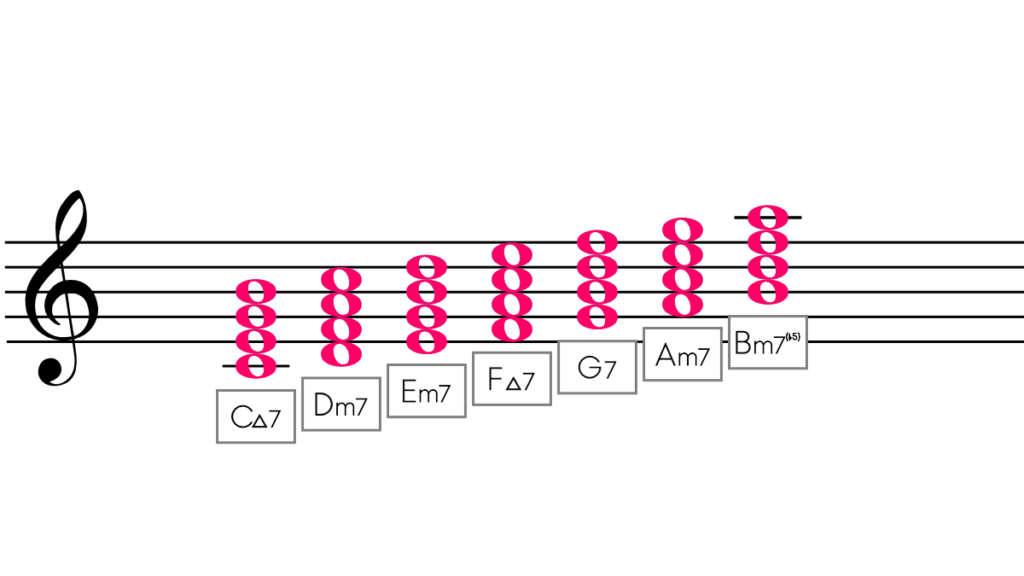
それぞれのコードにコードネームを振ってみました。
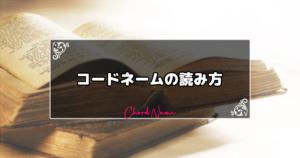
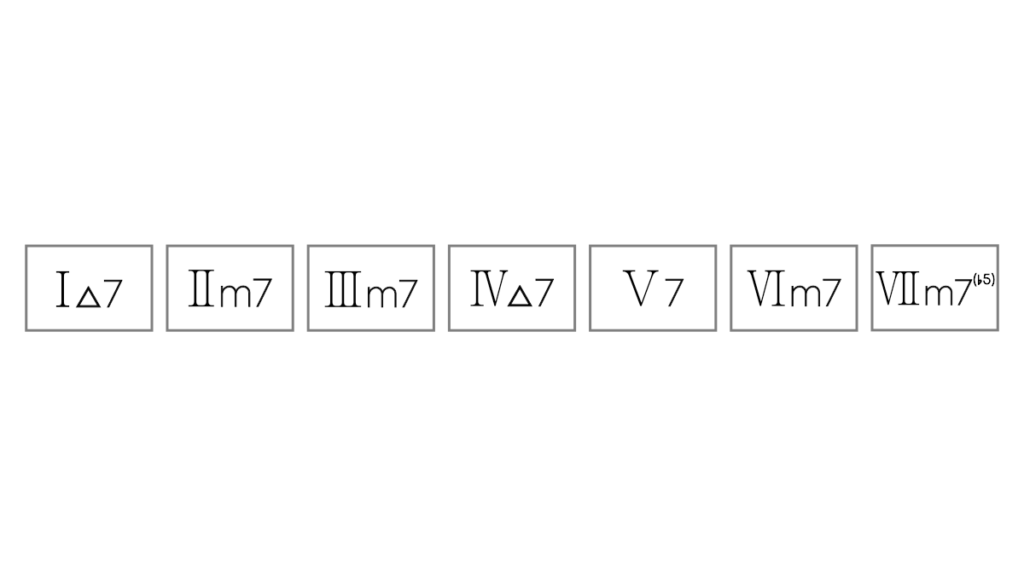
ディグリーネーム( = 度数表記)に変換してみました。
これがダイアトニックコードの本質の部分です。
メジャースケールを元にダイアトニックコードを生成すると、インターバルの関係で自動的にこの配列の7つのコードが出来上がります。
1度メジャーセブンス
2度マイナーセブンス
3度マイナーセブンス
4度メジャーセブンス
5度セブンス
6度マイナーセブンス
7度マイナーセブンフラットファイブ
これを丸暗記しましょう!!
僕が音楽の専門学校で勉強していた頃、90分かけてこの配列を丸暗記させられる授業がありました。
「ドー、レー、ミー、ファー、ソー」の音階で「1度メジャー、2度マイナー、3度マイナー、4度メジャー、5度セブンスー」と丸暗記します。
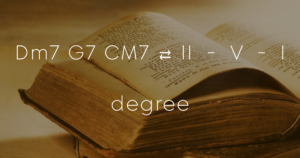
マイナーのダイアトニックコード
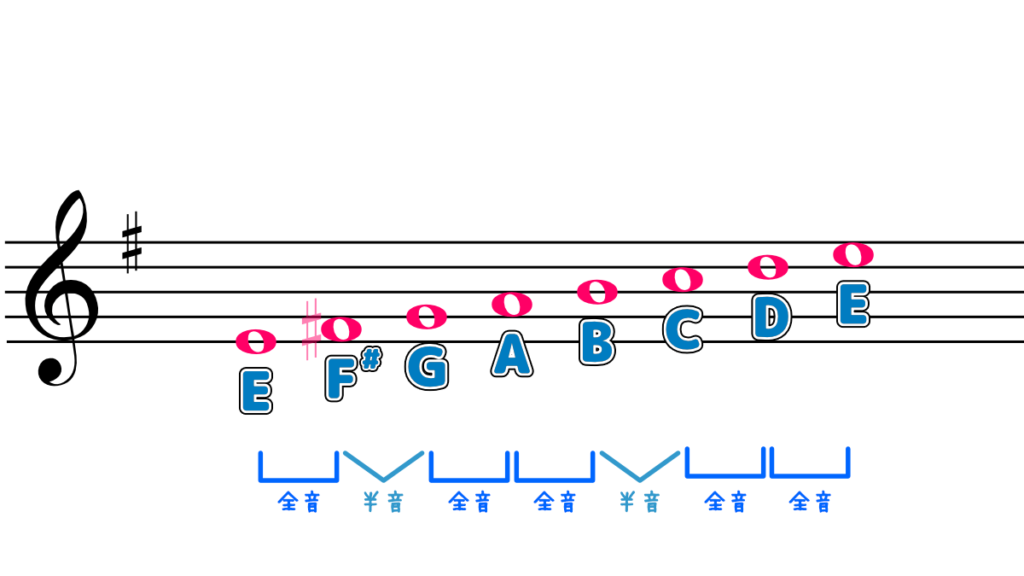
マイナーKeyの場合も作り方は一緒です。
メロディの基準になるスケールを用意します。
今回はEマイナースケールを用意してみました。
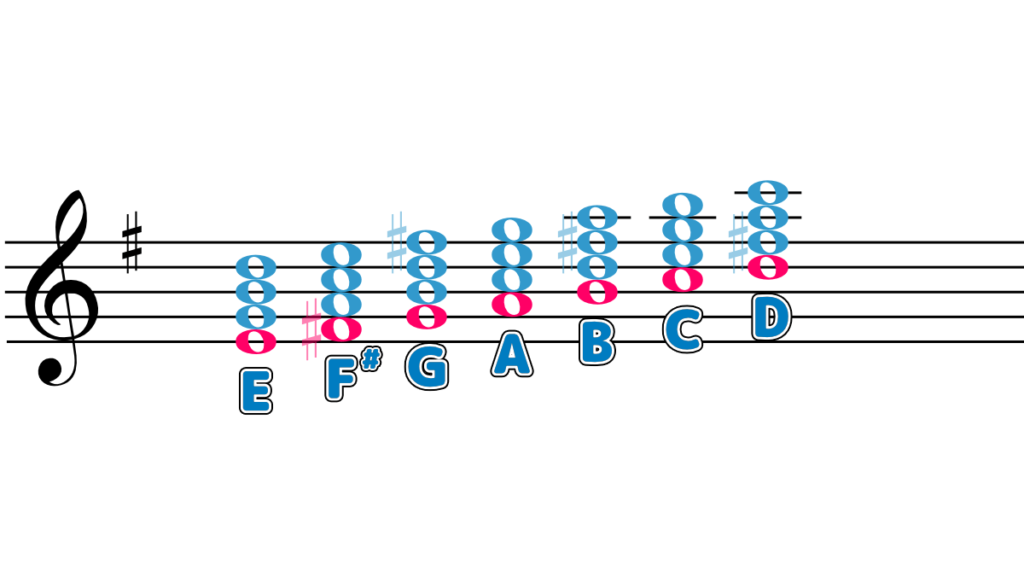
スケールの各音のうえに、1つ飛ばしで音を3音ずつ重ねていきます。
Eの上にはG,B,D、
F#の上にはA,C,E、
Gの上にはB,D,F#、
というように、スケールの音をひとつ飛ばしで重ねていきます!
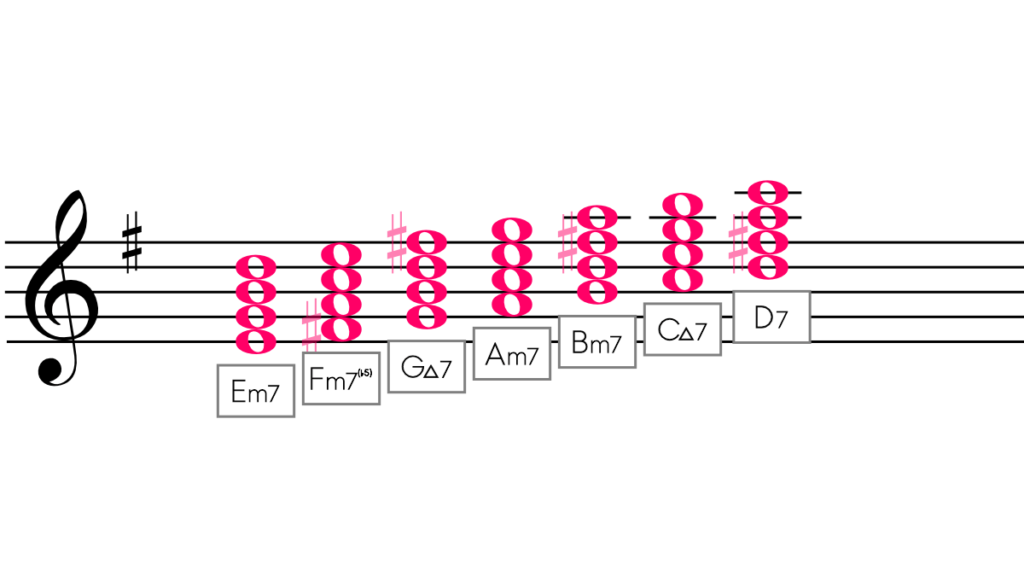
すると、根音として最初に用意したスケール(Key)に対応する7つのコードが完成します。
これがマイナーKeyのダイアトニックコードになります。
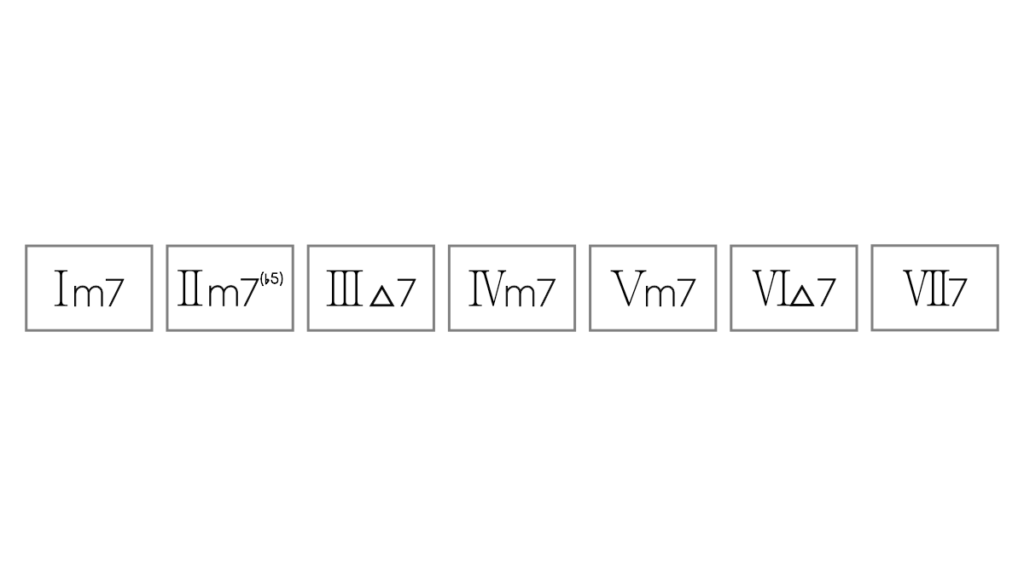
マイナーダイアトニックコードをディグリーネームに変換して抜き出してみました。
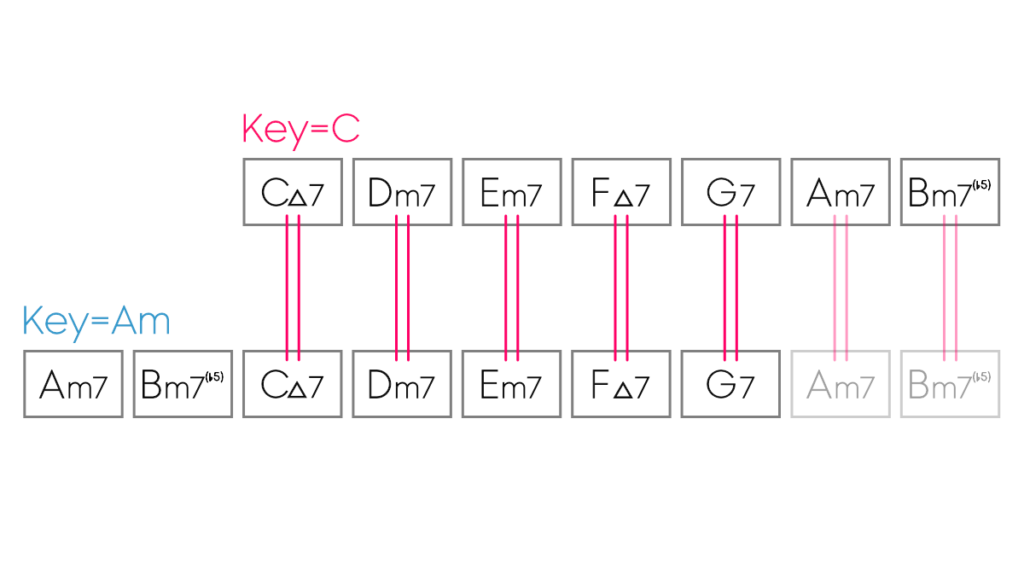
平行調を想定して考えると、メジャーのダイアトニックコードだけ覚えておけばマイナーのダイアトニックコードを導き出せるようになります!
なので、マイナーのダイアトニックを暗記する優先度は低いです。
詳しくは「平行調とは」の記事で解説しています!
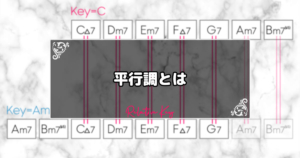
コードの機能(ファンクション)について
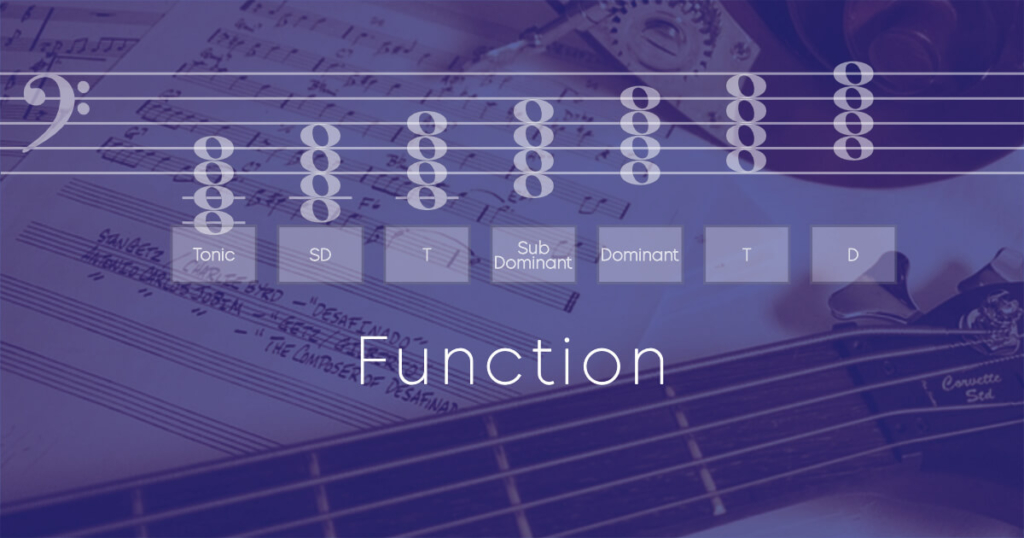
ダイアトニックコードの知識とあわせて勉強していただきたいのが「コードの機能(ファンクション)」です。
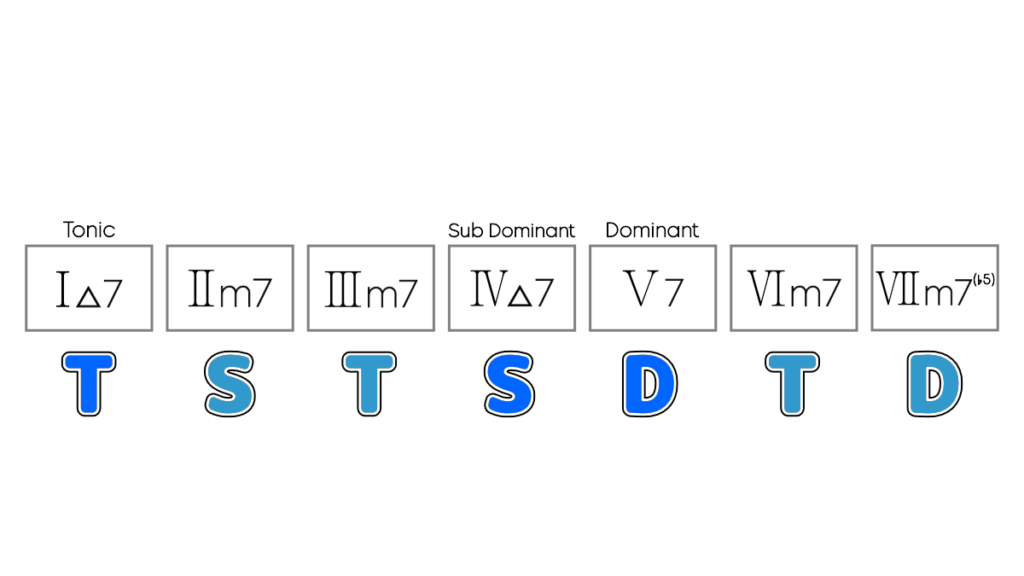
7つのダイアトニックコードには、それぞれに
- Tonic (トニック)
- SubDominant (サブドミナント)
- Dominant (ドミナント)
と呼ばれる特性=機能が備わっています。
必修科目なので、必ず身につけましょう!
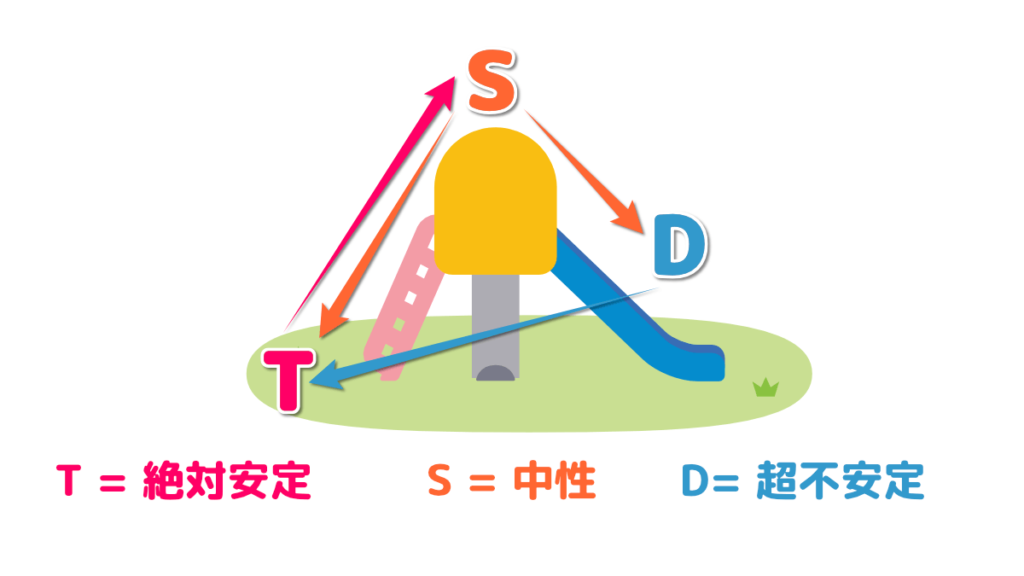
コードの機能が理解できるようになると楽曲のコード進行を感覚的に先読みできるようになるので、初見の曲でもリアルタイムに演奏できるようになってきます!